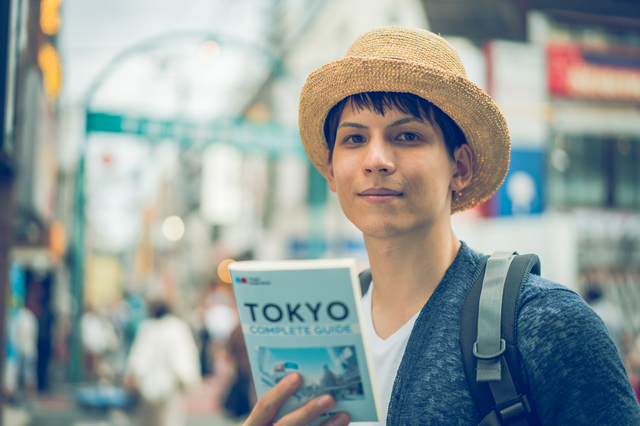この記事は最終更新日から1年以上が経過しています。内容が古くなっているのでご注意ください。
はじめに
観光産業は、“世界最大”の産業でした。新型コロナが猛威を振るうまでは……。実はそれまでは世界中で、なんと年間14億人以上のひとが観光目的で、国境を越え行き来をしていたんです。しかもその数、この7年間で40%も急増! 東京オリンピックに向けてインバウンド消費を期待していた日本にとっては、明らかに大きな痛手です。でもこれは、もしかすると観光業そのものが、新たなスタイルへと変化する絶好のチャンスかもしれません。多面的な視点で世界の文化やビジネス、人間そのものをしっかり観察すれば、ニューノーマルな観光業の理想の姿が見えてくるかもしれません。
立教大学観光学部の観光学はビジネス以外、文化や価値観の視点も重視

新型コロナによって、ひとの移動や交流が制限され、宿泊・交通など観光業の基盤が大きくゆらいでいます。けれど観光に関わるのは、もちろんそれらのビジネスだけではありません。
観光学のビジネス以外の側面まで多面的に捉える立教大学観光学部では、3つの視点で学ぶことができます。ひとつは「ビジネスとしての観光」。いわゆる旅行のプロセスで発生する宿泊・交通・飲食・エンターテイメントなどのビジネスの視点から。
そして「地域における観光」。どうすれば観光客がたくさんやってくるか。観光客を楽しませるには?居心地よくするには?さらに観光地である地域社会との影響は?といったことが対象です。
最後の視点は「文化現状としての観光」。そもそも私たちは、なぜ旅に出るのか。異国の地に惹かれてしまうのか。そこにはどんな価値観があるのか、なんてことを考えます。海外での少数民族の生活文化や遺跡修復など、国内外を問わずフィールドワークなども交えて、新たな価値観や行動様式を発見していくのも醍醐味だそう。観光といっても、いろんな学び方があるんですね。
経営や起業だって、アフターコロナ時代の“新しい観光”にとっては重要な要素

立教大学観光学部は「観光学科」と「交流文化学科」という2つの学科があります。「ビジネスとしての観光」について学ぶのが観光学科。「地域における観光」については、観光学科と交流文化学科の両方で学びますが、観光学科では「地域づくり」がメインテーマ。
経営、マネジメント、マーケティングなどの観点から観光を学びます。卒業生のなかには、商社に勤め、海外発電所の投資事業に携わっているひとも。在学時に学んだ“ホテル投資”についての知識が、投資対象は違うけれど共通点も多く、ビジネスの現場で活かされているそうです。新たな観光ビジネスを生み出し盛り上げるには、起業家や地域振興のリーダーとして周囲をひっぱっていけるようなリーダーシップが必要不可欠。そんな想いがベースにあります。
新型コロナによって生まれた“ニューノーマル”と呼ばれる社会では、これまでと同様の観光ビジネスの在り方は、もうないかもしれません。新しいビジネスを創りたい!そんなひとには絶好のチャンスではないでしょうか。
そもそもひとは、なぜ住み慣れた土地を離れ、未知の土地へ憧れるのか

「文化現象としての観光」として、文化や地域をつなぐ国際人の育成を目指すのが交流文化学科。異文化理解が、とっても重要です。
たとえば、新型コロナ対策問題。いま世界中の首脳陣が、この同じひとつの難題に頭を悩ませています。その対策は皆さんもニュースなどでご存知のとおり、国によってさまざま。即刻、都市封鎖を行う国もあれば、けっして封鎖をしない独自の対策を打ち出した北欧の国々もありました。
国によってさまざまな判断軸があるのは、脈々と流れてきた歴史や文化背景の違いが影響しているのは確かでしょう。背景には厳しい寒さや暑さなど気候条件の影響も含まれます。包括的な異文化理解が重要なんですね。
現在、地方公務員として地域コミュニティの課題解決やコミュニティ運営・管理などを担当している卒業生曰く「ゼミで身につけた、自分で考え必要な行動を選択するという姿勢が、非常に役に立っている」。「地域における観光」というテーマでは「地域のありよう」を中心に学びますが、実際に社会に出てから活用できる実践的な学びが多いようです。
専門性を核に、幅広い教養に触れる立教大学のリベラルアーツ

そんな立教大学のルーツは、1874年(明治7年)に宣教師であるチャリング・ムーア・ウィリアムス主教が聖書と英学を教える私塾として始めた「立教学校」です。創立以来、立教大学がいまも貫いているのが、キリスト教に基づく教育とリベラルアーツの理念。リベラルアーツとは「自由に学問を探求する精神」のことで「課題に向き合う思考力や変革力、異なる価値観を持つ人々と共に生きる力」だと立教大学は教えています。創立から100年以上がたったいまも開学の精神にゆらぎのない由緒ある立教大学。著名人も多く排出したその学び舎へ、あなたも一歩、足を踏み入れてみませんか。
歴史も文化も“京都”考察が未来のカギに! 同志社女子大学独自の観光学

同志社女子大学は「キリスト教主義」「国際主義」「リベラル・アーツ」に基づき、「21世紀社会を女性の視点で「改良」できる人物の育成」をVisionに掲げ、真に女性が輝く社会づくりをめざす大学です。社会の中で観光という要素は、人が地域社会と複合的に交流し、多文化交流を通して新しい地域像をつくり出していくプロセスです。地域振興においても大切な課題であり、持続的な社会づくりを考える上でも重要です。
現代社会学部社会システム学科の「京都学・観光学コース」では、国際観光もふくめた広い視野で、地域形成の重要な役割として観光を捉える総合力を養っています。さらに、大学がある京都という地域を歴史学・地理学・観光学など広領域からの視点から総合的に考える京都学を設置しているのが大きな特色。京都を考察すれば、他の地域や日本の歴史が形成される過程を探ることにもつながります。
観光とは、経済・地理・歴史・文化を複合的に考察する学問。国際観光都市“京都”をこのように多角的な視点で捉える力は、観光に限らず地域産業や地域活性化、町づくりなど幅広い分野にも活かすことができるでしょう。まさにアフターコロナ時代の社会に必要な力かもしれませんね。
在学中から実践的地域活性化プロジェクトにも参加! 跡見学園女子大学

1875(明治8)年の学園創立以来、専門性と豊かな教養を持ち、自律・自立した女性を育成してきた跡見学園女子大学。観光コミュニティ学部観光デザイン学科は、「観光で日本を元気にする」をテーマに「観光デザイン能力」を発揮できる人材を育成しています。
観光デザイン能力とは観光を具体的に構想できる能力のことで、3つの力に支えられています。まずは、地元の人は気づいていない地域の魅力を、掘り起こして情報発信する「発掘発信能力」。次に、観光客をおもてなしする「ホスピタリティ能力」。そして観光施設を継続的に運営する「マネジメント能力」です。観光を創造し、コミュニティを活性化することで、地域の基幹産業に加えて「観光地」として発展できます。
特徴的なのは、座学で身につけた知識を活用して、民間企業や自治体とともに地域活性化のためにおこなう「産官学連携プロジェクト」。これまでにも多くの学生が多彩な活動に取り組んでいます。これらの能力は旅行・航空業界、ホテルやリゾート、自治体や公共機関の観光関連事業で活躍できます。観光客とコミュニティをつなぎ新しい日本をデザインするなんてワクワクしますね。
おわりに
観光学にはさまざまな視点があり、観光を軸に多様な知識やスキルを学べるユニークな学問であるのはご紹介したとおりです。新型コロナによって大きな変革のまっただなかにあるといえる観光業だからこそ、観光をとおして新しい社会を創りだす絶好のチャンスだといえるかもしれません。