この記事は最終更新日から1年以上が経過しています。内容が古くなっているのでご注意ください。
はじめに
皆さんは、高校で「生物」「化学」「物理」をそれぞれ別々の科目として選択して学んでいますよね。けれども科目というのは、その学問の基礎を「学びやすく」また「教えやすく」するために設定されているもので、ひとつの物事や現象は、生物学的な側面・化学的な側面・物理学的な側面を合わせ持っています。だから、大学でのハイレベルな学びになると、高校までの理系科目の領域が融合した内容となり、幅広い知識や物の見方が必要となるんです。
生物学と情報学の境界領域にあるバイオインフォマティクスとは?

「大学でバイオを学ぶ」と聞くと、生物学を専門的に極めるというイメージを持つ人が多いかもしれません。けれども実際には生物学のみを学ぶのではなく、医学・薬学・理学・工学・情報科学など、多くの分野が関わる知識が求められます。
例えば「バイオインフォマティクス」とは、バイオ(生命科学)とインフォマティクス(情報科学)の接点にある学問です。DNA・RNA、タンパク質をはじめとする生命が持つ様々な「情報」に対し、情報科学や統計学を使ったソフトウェアを開発し、分析して、生命現象を解き明かしていきます。生命科学と情報科学は全く異なる学問でしたが、遺伝子のゲノム解析によって急速に両者の距離が接近し、境界領域に新しい学問としてバイオインフォマティクスが誕生したのです。
こんな風にバイオの周囲には多種多様な学問が次々に生まれています。つまり新しい可能性がどんどん出てくる分野だといえます。そんな学問に、大学から取り組んでみたいと思いませんか?
バイオが開く未来はこんなに幅広い?! 神奈川工科大学応用バイオ科学部って?
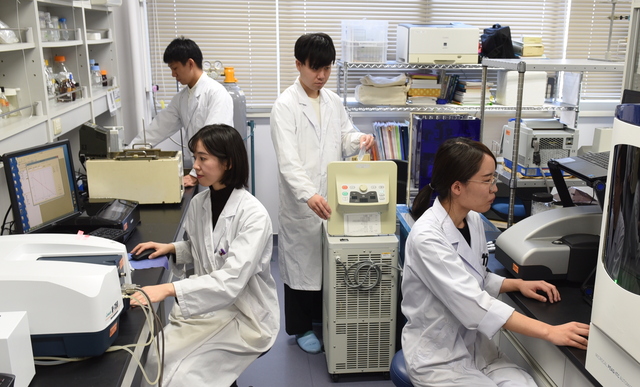
神奈川県厚木市にキャンパスがある神奈川工科大学は、5学部13学科を設置する理工系総合大学です。応用バイオ科学部応用バイオ科学科には、応用バイオコースと2020年度に新設された生命科学コースの2学科があります。
応用バイオコースは、技術者としての知識とスキルを身につけるために、1年次から実験と授業が融合したユニットプログラムが用意されています。2年次後期からはさらに専門性の高い実験科目に取り組み、微生物・動植物細胞の取扱いとその観察方法、遺伝子組み換えや生理活性物質の合成等の技術、機器分析技術、先ほどご紹介したバイオインフォマティクスに関わる情報処理技術等を習得できます。また生命科学コースは、分子・細胞・組織のさまざまな階層で生命を捉える視点を養います。1・2年次には化学・生物学・物理学・情報科学の基礎分野の講義と実習を積み重ねて論理的思考力や発想力を習得し、3年次からは生命化学・生物科学領域の専門的な内容を学びます。
卒業後は「医薬・ライフサイエンス」「食品・植物科学」「環境・微生物学」の3分野を中心に、食品、化学、医薬/医療、化粧品、エネルギー関係、精密機械など幅広い産業界で活躍しています。また、研究者としての道もあります。「バイオ=生物」というイメージが、変わりそうですね。
「自主テーマ実験」「バイオコンテスト」で個性や長所を発見!

神奈川工科大学応用バイオ科学科には、バイオ技術者や研究者として、自らの個性や長所を発見して伸ばすための機会が設けられています。
特徴のある授業として、自分たちで研究テーマを考え、実験をデザインして実践する「自主テーマ実験」や、1年次から研究室に入門して自分の取り組みたい実験を行う「課題研究」があります。実験の成功体験はもちろん、失敗もしながら原理をしっかり理解し、研究者としての力を養うことができます。また、楽しみながらバイオの世界を学べる教材を作る「バイオコンテスト」の授業では、学生が考えた教材を小学生などに実際に体験していただき、その出来映えを実感することができる全国の大学でも珍しい取り組みとなっています。
自分の興味や個性を探り、それを開花させるためのチャンスがたくさんあるので、学び進むほどに目標が明確になりそうですね。
高度な研究や実験に取り組める機器や施設が充実!

充実した機器や施設も神奈川工科大学の特色です。バイオサイエンスセンターには、外部から遮断された状態で微生物の操作ができる「クリーンベンチ室」、微生物の培養を行う「培養室」、化学や分析関係の技術を習得できる「バイオ実験室」があります。さらに機器分析室には生体関連物質の分析を行う多種多様な装置を配備し、高度な分析に使われる機器を学生が使うことができます。バイオメディカル研究センターには、細胞や組織を経時的に観察できるタイムラプスイメージングシステム、特定の細胞を取り出すことのできるセルソーター、薬剤をタンパク質やRNAなどに結合させる際に使われる等温滴定型カロリメトリーなど、医薬品開発や医療技術開発の基礎研究に必要な実験設備もあります。
多種多様な学問領域を学び、各領域で使われる実験施設や設備を使いこなす技術と知識を身につけることで、幅広い分野で活躍できる力を養うことができるんですね。
省資源・低コストで「地球を救う触媒」を開発する工学院大学

東京都内に2つのキャンパスを有する工学院大学。理系総合大学として、先進工学部・工学部・建築学部・情報学部の4学部15学科を擁しています。
応用化学科の触媒化学研究室では、新しい触媒の開発に省資源・低コストで取り組んでいます。触媒とは、何段階もある化学反応の反応速度を速める物質のことです。研究室では特に取扱いが容易な固体触媒に注目し、有害物質を出さないプロセスを開発しています。実用化されれば、地球環境を守ったり、必要な物質を作ったり、希少資源の使用量を減らしたり、エネルギー資源を有効に使ったりできるのです。例えば、最近注目されている燃料電池自動車の燃料・水素を石油などから効率よく製造するための触媒や、健康リスクが高まるとされている「トランス脂肪酸」を含まないマーガリンを作る触媒の開発をしています。また、触媒の原理を理解するために、兵庫県のスプリングエイトや茨城県のフォトンファクトリーなど世界屈指の研究施設での実験も行います。
触媒を追究することで、全人類が直面するSDGsに関わる課題もたくさん解決できそうですね。
「実工学」を推進する日本工業大学

1907(明治40)年創立の東京工科学校をルーツに持つ日本工業大学。社会に役立つ「実工学」を推進していて、基幹工学部応用化学科でも様々な実工学が追究されています。
材料科学系の固体電気化学研究室では、全固体電池の研究をめざしています。私たちもよく使うリチウム電池は、正極と負極は固体ですが、その間の電解質は可燃性の液体です。この電解質を結晶性の高品質薄膜の作製によって固体にすることで、安全性に優れた電池となります。この技術を電気自動車等の大型バッテリーへの応用することも期待されています。また、生物工学系のナノ機能デバイス研究室では、ナノ粒子を分子で覆うことで生じるナノ粒子集合体の構造を探索し、その集合体をバイオ関連やセンサーとして応用することをめざしています。また、こうしたナノ粒子に抗原や核酸などの生体分子を固定化し細胞に取り込ませ、その取り込み量や免疫応答を調べることで、効率の良い薬剤輸送キャリアやワクチンの設計指針にもつながります。
研究の成果が、私たちの生活につながる「実工学」であるだけにやりがいも大きそうですね。
おわりに
高校で学ぶ理系科目は科目別に分かれていましたが、大学ではそれらが融合したり接したりする領域を学ぶため、幅広い知識が必要なことをご紹介してきました。あなたが「これこそ自分の得意科目!」と自信を持って言えるものがあるなら、その科目がどんな分野と関わっていくのかを調べてみることをおすすめします。大学での研究テーマが見えてくるかもしれませんね。



