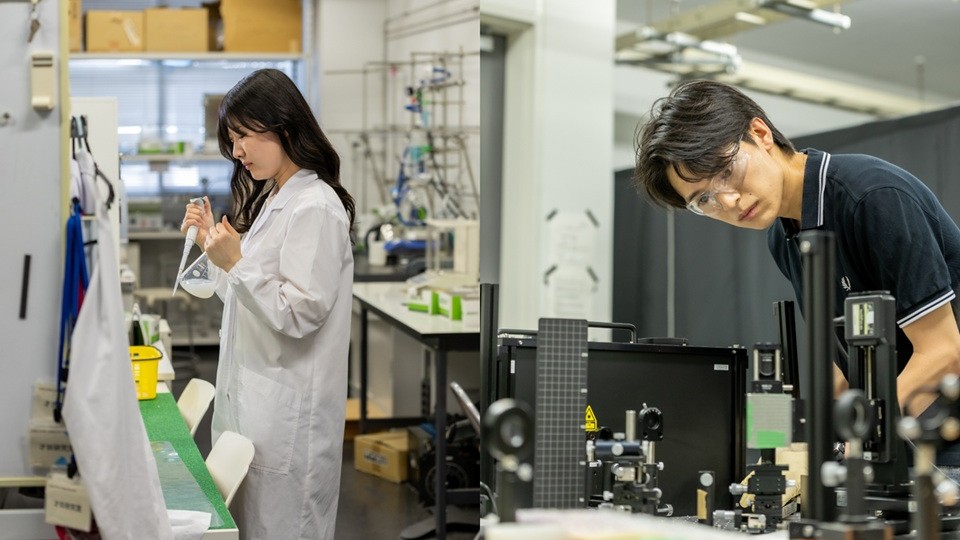はじめに
ひと口に“理系”といっても大学で専門的に学べる内容は様々ですが、皆さんが興味をもっているのはどの分野でしょうか?
今回は、皆さんの進学先選びの参考にしてもらうため、数ある理系分野の中でも「化学」と「物理」の魅力にクローズアップ。大学卒業後は大学院へと進み、さらに専門的な学びを追究している先輩たちにインタビューを行い、学科選びのきっかけや大学で体験できる最先端の研究、学びを通じて得られた将来につながる“強み”などについて語っていただきました。
先輩たちが語る、化学や物理の“おもしろさ”との出会い!

今回、インタビューにご協力いただいたのは、名城大学の大学院で学んでいる根岸真由さん(理工学研究科応用化学専攻)と齋藤巧夢さん(理工学研究科材料機能工学専攻)。そもそも、おふたりはどんなきっかけから物理や化学を“おもしろい!”と感じるようになったか、早速、お話をうかがってみましょう。
根岸さん:化学に対する最初のイメージは“暗記科目”でしたが、高校の授業で聞いた有機化学の話をきっかけに表面的な理解から一歩踏み込んで、「原子がどの位置でどう結びついて、どのように反応が進むのか」といった反応の仕組みを知ったのが衝撃的でした。
齋藤さん:小学生の頃から理科は好きでしたが、物理のおもしろさを感じるようになったのは高校生のとき。たとえば、電車で体がふられるのは「慣性の法則」、救急車のサイレンの「ドップラー効果」といったように、授業で学んだことが日常生活の実体験と結びついたのがきっかけです。
幅広い学びがあるから自分の夢中になれるものが見つかる!

先生のふとした話を自分の身のまわりのことに置き換えてみたり、新たな視点でものごとを見てみたりすることで、化学と物理への興味を深めていった先輩たちですが、数ある大学の中から、なぜ今の進学先を選んだのでしょうか?
根岸さん:名城大学を選んだのは、実験や研究にしっかりと取り組める環境が整っていたからです。高校の時点では明確な目標が定まっていなかったので、幅広い学問領域を有している化学を専門的に学べる「応用化学科」なら、自分が夢中になれる何かを見つけられると思いました。
大学での学びは、知れば知るほど新たな疑問や興味が生まれます。今ではそうした探究のくり返しこそ、化学を学ぶ醍醐味だと思っています。同じ実験でもグループごとに異なる結果が出ることもあり、「実験ってこんなに繊細で難しいものなんだ」と感じると同時に、逆にそこにおもしろさを感じました。
齋藤さん:大学では物理を学びたいと思っていましたが、専門分野が細かに分かれていたため、どこに進むべきか悩んでいました。そのなかで名城大学の「材料機能工学科」では、「エレクトロニクス材料系」「応用物理系」「機械材料系」の3分野を1~2年生のうちに幅広く学んだうえで、最も興味のある分野を選べる点に魅力を感じました。
ただ、実際に学びを進めていくと、それぞれの分野が深くかかわり合っていることに気づかされ、研究には多くの分野の知識だと実感しました。また、実験や実習が豊富なので、「講義で習ったことが目の前で起きる」ことが楽しくなり、思っていた以上に学科の学びにひき込まれていきました。
幅広く学びながら、社会に通用する専門知識とその応用力を養えるだけでなく、実験や実習を通じて、将来、自らの手で新しい分野を創造的に切り開いていく技術者を育成していくのが、先輩たちが選んだ応用化学科と材料機能工学科の特長です。2026年からは、ふたつの学科が「化学・物質学科」に統合され、「応用化学専攻」「材料機能工学専攻」の2専攻体制へと移行されます。
最先端の研究を支える化学と物理の融合

新たに開設される「化学・物質学科」では、化学と物理が融合した最先端の研究が展開されていきますが、先輩たちも研究を通じて、その密接なかかわり合いを感じたといいます。そうした気づきは、どんな出来事から得られたのでしょうか?
根岸さん:私は、持続可能な社会の実現の一助となるような研究がしたいとう思いから、水素製造に関する研究を行っています。水素は水の電気分解によって得られますが、実はその化学反応を理解するには、水分子の吸着挙動や電子の授受など化学と物理の両面からの理解が欠かせません。また、X線回折などの分析手法にも物理への理解は必要で、化学と物理は密接にかかわっていると実感しています。
齋藤さん:材料機能工学科は、青色LEDでノーベル賞を受賞された赤﨑先生がかかわった学科です。私もそうした発光デバイスに強い興味をもったことから、医療・工業・環境など様々な分野で注目されている「紫外光の半導体レーザーダイオード」の研究を行っています。そして、私の研究には化学と物理のどちらも欠かせません。たとえば、結晶を成長させるときや、加工するときに使っているのは化学の知識。一方で、材料の性質を理解し、正しく評価するためには、物理の知識がとても重要です。
「化学・物質学科」では、分子・原子レベルから新規物質・材料の設計および合成という、化学と物理が融合した最先端の研究により、先輩たちのように、未来の世界に貢献していく研究者や技術者の育成をめざします。
研究を通じて得た将来への“強み”とは?
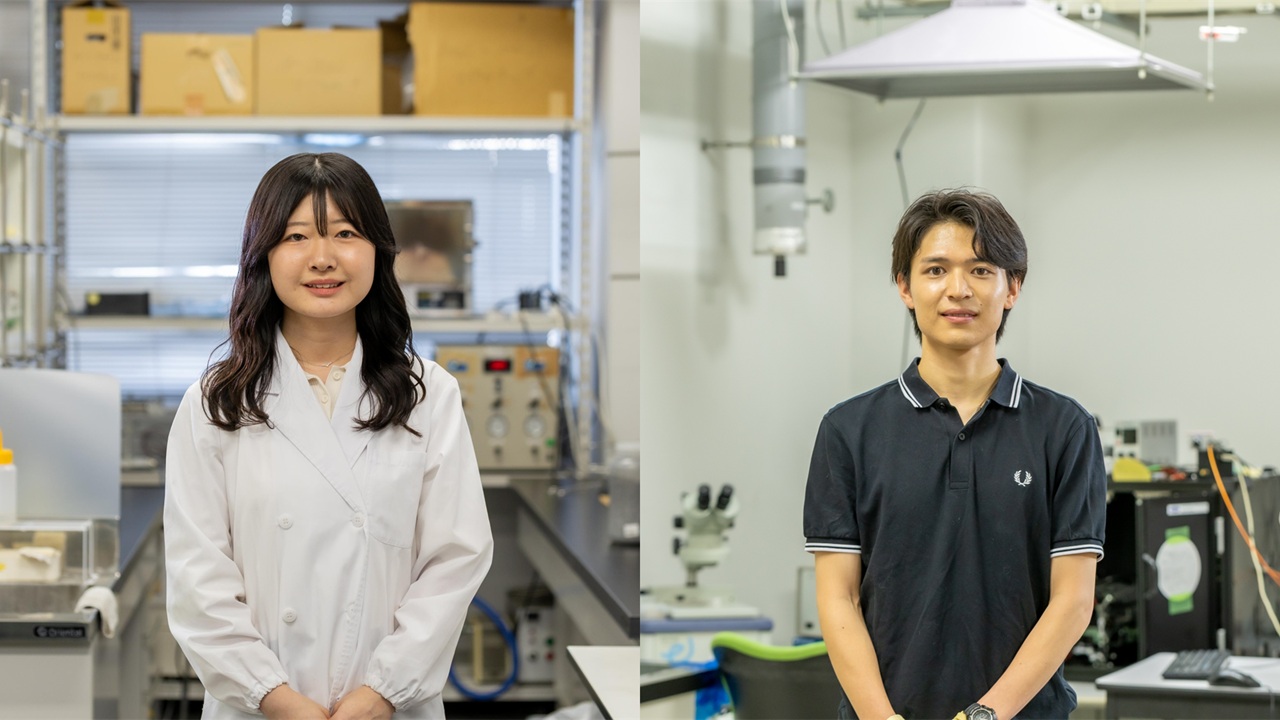
最後に、先輩たちは大学での学びや研究を通じて、どんな“強み”を身につけることができたのか。高校生へのメッセージと合わせて、聞いてみました。
根岸さん:研究室に所属するようになると、実験の結果について議論したり、発表の準備をしたりするなかで、論理的に伝える力が鍛えられました。その経験は就職活動でもとても役に立ち、面接などでもあわてることなく、自分の考えを相手にわかりやすく伝えることができるようになったと思います。
私自身、大学に入学した時点では特に「これがやりたい!」という明確な目標はありませんでしたが、学んでいくうちにおもしろいと感じる分野にたくさん出会えました。ですから、化学に興味がある高校生の皆さんも、名城大学で学ぶなかで「これだ!」と思える何かがきっと見つけられると思います。
齋藤さん:大学で様々な分野を横断的に学んだ経験は、新しいことを学ぶ力につながりました。また、半導体レーザーに関する研究で、ひとつのものをゼロから作り上げる経験は、問題解決力や計画力、チームで動く力という、社会で求められる力を伸ばすことに役立ったと思います。
さらに大学では理論だけでなく、実験やものづくりを行う経験が加わることで、「知識」が「自分の考える力」として定着したと実感しています。特に、化学や物理の分野では、実際に目で見たり触れたりできる現象をもとに考えることが多いので、「なんでこうなるんだろう?」という疑問を調べることが楽しいと思える高校生には、とても向いている研究だと思います。
「先輩たちが所属する応用化学科※と材料機能工学科※は、いずれも就職率が100%(2025年3月卒業者)に達しています。両学科ともに自動車関連企業や大手メーカへの就職だけでなく、大学院に進学する学生も多くいます。
※2026年4月より化学・物質学科「応用化学専攻」「材料機能工学専攻」に変更
おわりに

先輩たちのお話は、皆さんの進路選びの参考になりましたでしょうか?
今回のお話をきっかけに名城大学や新たに開設される化学・物質学科に興味をもった方は、ぜひオープンキャンパスに参加してみてください。理工学部の置かれた天白キャンパスでの開催日時は8/2(土)・8/3(日)。詳しい情報に関しては下記のサイトに掲載されていますので、ぜひチェックしてみてください!